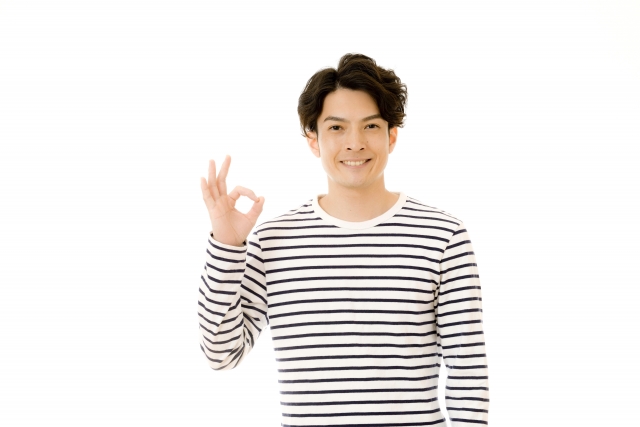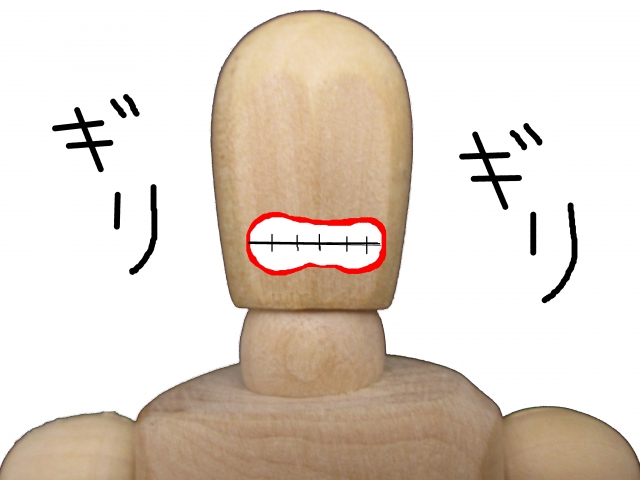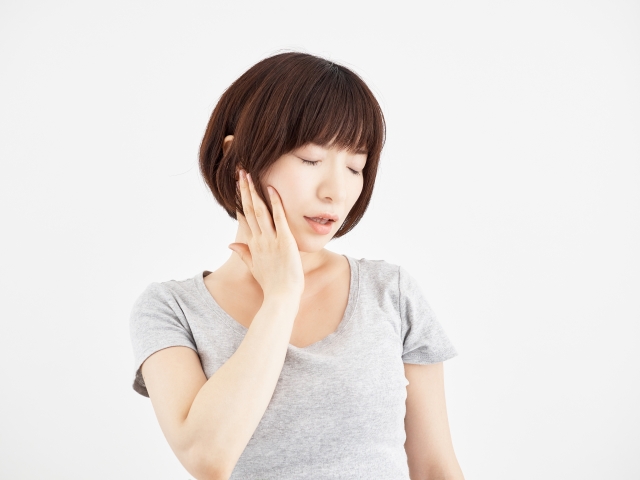年齢と共に身体の機能がだんだん衰えてしまうことは自然なことです。
しかし、顎に関してはどうでしょう?
顎は年齢に関係なく伸び縮みするとは思いづらいですが、顎が昔と比べて伸びたことによって顔全体の印象が変わったことを気にする男性がいるようです。
そこで、本当に顎が伸びることがあるのか、考えられる原因と対策についてお話ししていきます。
顎が本当に伸びることはあるのか?
顎は固い骨格でできているため、大人になったからといって大きく伸びるようなことはない気がしますよね。
しかし、実際に伸びているように感じている男性もいらっしゃるようですので、どういうことなのか検証してみましょう。
まず、結論としていえるのが、顎が伸びることは本当にあるようです。
そして、それが病気によってなってしまう場合があるのです。
先天的な病気である「顎変形症」と、後天的な病気である「顎関節症」です。
また、他にも考えられることが分かりました。
それは、普段何気なく行っている生活習慣によるものです。
それでは、次項から順番にご説明していきます。
顎の長さが気になってしまうことから少しでも早く解放されるよう、原因と対策について一緒に探っていきましょう。
顎が伸びる顎変形症!原因と治療法
顎が伸びる症状として考えられるものに、「顎変形症」があります。
顎変形症は特に定まった原因特定が難しく、ほとんどが遺伝的なものだとされている病気です。
顎の骨は、上顎骨・下顎骨・頬骨の3つから成り立っていますが、顎変形症の場合、顎の骨に異常が見られます。
たとえば、顎の骨の形や大きさが異常だったり、位置が適当でないことなどです。
顎のバランスが崩れてしまうため、噛み合わせの悪さや話づらさを訴えることもあります。
顎変形症の種類は、上顎前突症・下顎前突症・開咬症・非対称症・上下顎前突症・下顎後退症などがあります。
日本人の多くは、下顎前突症の割合が多いということです。
下顎前突症は中学生ごろに下顎骨が生長しすぎることが多く、それ以降は下顎が少しずつ伸びるように出てくるようです。
顎変形症が疑われる場合は、形成外科や矯正歯科などで相談することになります。
治療は症状がひどくなければ、矯正歯科による噛み合わせの矯正から始まります。
しかし、骨格の変形がかなり進んでしまっている場合は、歯の矯正と合わせて骨を切断するような外科手術をするのが一般的です。
顎変形症だと診断されると、歯の矯正や手術代は保険が適用されることになっています。
具体的には医師とご相談ください。
後天的な原因から!顎関節症で伸びる顎
顎変形症は遺伝が大きな原因である場合が多かったのですが、顎関節症は後天的な原因で起きます。
どのような原因があるのかお伝えしていきます。
〇考えられる原因
・歯ぎしり
・食いしばり
・歯並びの悪さ
・噛み合わせの悪さ
・ストレス
〇主な症状
・口の開閉時、顎で音がする
・口が開けにくい
・口の開閉時、顎や耳に痛みがある
上記の症状があって、他に直接の原因が思い当たらない場合は、顎関節症だと診断されるようです。
顎の筋肉が痛む場合は、歯ぎしりや食いしばりが原因である場合が多く、顎の筋肉が緊張してコリがある状態です。
そして、顎関節の軟骨が変形したり関節がずれたりしていると、顎関節炎として痛みが生じます。
口を動かすだけでも痛くなると、食事の際にも支障がでてきます。
また、口の開閉に大事なのは関節円板ですが、これがずれることにより開閉がしづらい症状がでます。
歯並びの悪さや噛み合わせの悪さだけが原因であれば、歯の矯正を行うことで症状が良くなるはずです。
しかし、顎の骨もずれている場合は顎の治療もしなければなりません。
顎関節症は症状が進んでしまうと、顎や顔にゆがみや変形を与えることがあります。
もしかすると、顎が伸びるように感じているのは顎関節症によるものかもしれません。
顎関節症は顎周りの症状だけでは済まないことも!原因は?
顎が伸びる原因について探ってきましたが、顎関節症は顎周りの症状だけではなく、身体の他の部分にも症状が出てしまうことがあります。
〇顎関節症による顎周り以外の症状
・頭痛や片頭痛
・肩や首のコリや痛み
・耳の痛みや耳鳴り
・身体のしびれ
頭痛や片頭痛は普段から症状がある男性も多いですが、顎関節症が原因のことも考えられます。
顎の筋肉は頭の横にある側頭筋と繋がっています。
顎の筋肉のコリが側頭筋のコリに繋がり、緊張状態が続くことによって片頭痛などをもたらすと考えられているのです。
また、顎の筋肉は肩や首と繋がっており、やはりコリが広がってしまうことがあります。
その場合に、肩や首にコリを感じたり痛みを生じることになるのです。
耳の痛みや耳鳴りは、耳の近くにある側頭骨と顎の関節が繋がっていることから起きます。
顎で起きてる炎症などがそのまま耳に通じてしまうのです。
身体のしびれは、顎の筋肉を使う力の強さによって現れます。
顎での緊張が身体中の筋肉に伝わり、しびれを伴うことになります。
顎が伸びる原因は日常の動作からも
顎が伸びる原因、先天的な顎変形症と後天的な顎関節症についてお話ししてきました。
ここからは、どちらにも当てはまらない生活習慣から起きやすい顎が伸びる原因について探っていきます。
〇机に頬杖する
仕事中や家で疲れて頬杖ばかりしてはいませんか?
頬杖は頭を手で支えますが、顎の上に頭の重さが全てかかるため、顎にずれが生じる場合があります。
そのまま続けてしまうと、顎が伸びるように変形してしまうことも。
〇噛む場所がいつも片側ばかり
食事をするとき、いつも決まったほうばかりで食べている場合、片側ばかりに顎の負担がかかります。
そして、長年この負担が続くと顎関節症になることがあります。
〇ストレスを抱えている
ストレスがない男性はいないと思いますが、あまりにストレスを抱え過ぎてしまうと、食いしばりや歯ぎしりをしてしまうことがあります。
食いしばりや歯ぎしりは顎の筋肉に相当な負担がかかり、顎のためにもよくありません。
歯ぎしりの場合は、歯科医での治療が一般的です。
顎の関節をほぐす方法
顎が伸びるのには、色々な原因が考えられました。
ここでは、どの場合にも効果が期待できる顎の関節をほぐす方法をご紹介します。
一日に3回くらいを目安に行ってみましょう。
忘れないよう食事時に合わせて行うといいかもしれませんね。
【顎の関節をほぐす方法】
①口を大きく開ける
②顎を出す
③顎を引く
④顎を右に動かす
⑤顎を左に動かす
それぞれ10~15秒ほどキープしてください。
痛い場合は無理をしないようお願いします。
もし、顎関節症などで症状が進んでいる場合は改善が難しいことも考えられます。
また、顎の痛みや違和感が他の病気などである可能性もありますので、心配なときはかかりつけの医師とご相談の上、実践してみてください。
かえって症状が悪化してしまうことのないよう注意しましょう。
顎が伸びる原因はひとつではない
顎が伸びる原因は、先天的な顎変形症や後天的な顎関節症が考えられました。
また、普段の生活習慣から起きてしまうこともあるようです。
普段の生活習慣から来ている場合はそれを改善するよう心がけ、顎の病気が疑われる場合は医師の診察が必要になります。
放っておくと、顎周りだけでなく全身への症状が出てしまう場合もありますので、対策は早めに行いましょう。